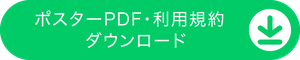西条農業高等学校 Team SSS ×愛媛大学社会共創学部井口梓研究室
テーマ「 うちぬき 」
「うちぬき」とは、霊峰石鎚山を源として、西条市内に自噴する清澄で良質な地下水で、以前は、人力により鉄の棒を地面に打ち込み、その中へくり抜いた竹を入れるだけで自噴する水を確保できていたことから「打ち抜き」呼ばれるようになりました。昭和60年(1985) 3月環境庁から「名水100選」にも選ばれる名水であり、西条市民の生活に深く根差しています。
みんなの野菜の洗い場
西条市上喜多川 野菜の洗い場
昭和40年代に上喜多川地区の農家らが共同して手作業で作った野菜の洗い場。背景に石鎚山系と田畑を臨み、西条市のうちぬきと農業をつなぐ伝統ある景観をつくりだしている。「20年ほど前は洗い場の取り合いだったんよ。」と、上喜多川地区で野菜作りをする83歳の農家が話してくれた。全盛期は、22個の洗い場を農家らが奪い合う状況で、野菜の出来栄えを競い合いながら洗っていたというが、時代が変わり農家数の減少などによって最近では洗い場を利用する農家は1日のうち3~4人と減少している。野菜の洗い場は上喜多川地区の農家にとって欠かせない場所であり、私たちが農業をより発展させていかなければと決意した。
潮ひきたる時 清水湧く
弘法大師の加持水なり
西条市 弘法水
本陣川の河口、海底の水源より清水が湧き出ている弘法水。弘法大師が四国霊場を巡礼している途中、老婆に一杯の水をもらった、遠方から汲んできたという苦労を思い、杖の先で強く砂浜を突くとそこから清水がこんこんと湧き出たという伝説が残る。見ての通り四方を海に囲まれているが、そこから湧き出る水から塩気は一切感じない美味しい真水である。現在、弘法水は喜多浜・港新地自治会が維持管理しており、弘法大師像を祀っている小屋には千羽鶴も奉納されていることから、地域住民の信仰の場にもなっている。生活用水としても利用している地域住民の中には長寿が多く、弘法大師の加持水のおかげかもしれないと言われている。
石鎚山 中山川
加茂川の豊かな水 禎瑞の実り
西条市 乙女川堤防と禎瑞
豊かな伏流水の源、西日本最高峰の「霊峰石鎚山」が雄大にそびえたつ水都・西条市は、県内有数の穀倉地帯である。乙女川に鎮座する「龍神社」には、海路安全や漁業繁栄などの海事一切の守護と各産業の隆盛、家内安全および豊作に必要な灌漑良好を願い海神さまが祀られている。神社の片隅にそっと置かれていた竹ぼうきから、今も地域住民から大切にされていることが伝わってくる。実りの秋には、乙女川の水で大きく育った稲の収穫、禎瑞小学校生が小船に乗り、地域の大人から手ほどきを受けながら伝統を引き継いでいく川狩り、そして豪華絢爛な西条祭りの始まりだ。このすばらしい景色・伝統をどうか守ってほしいと、龍神社での参拝で願った。
打出す清水は結晶の如く
西条市 嘉母神社の自噴水
嘉母神社のうちぬきは、西条市でも数少ない自噴水として西条市民に親しまれている。昭和60年には環境庁により名水百選に、平成7・8年の全国利き水大会では、全国1位のおいしい水に選ばれた。手水舎には「伊よの西条は御城下町かよ 石鎚山から流れる加茂川 神の水だよその又地獄の 岩を打抜くわしらの誇りの 打抜く家業は先祖代々 打出す清水は水晶の如く…」とかつてうちぬき作業に合わせて歌われていたものに、西条を顕彰する歌詞をつけた西條打抜音頭が掲げられている。歌詞に残るほどに愛された西条のうちぬき本来の姿が、ここ禎瑞の嘉母神社の地にしっかりと残され、地域住民の生活に寄り添いながらしっかりと現代に受け継がれている。
制作の様子
令和3年(2021) 11月3日のフィールドワークでは、農業高校生ならではの視点で農産品と「うちぬき」の関連に注目しました。地元農家の方々に「うちぬき」を使った地域での野菜作りの歴史や、野菜の洗い場などの話を聞かせていただき、興味津々に聞き入りました。洗い場に水が張られていく様子や手際よく野菜を洗っている様子に、歓声があがりました。高校生からは「野菜洗いを初めて生で見られてすごく嬉しい」、「地元なのに、このような歴史は知らなかった。貴重な話を聞かせてもらえた」などの声もあり、大興奮の様子。11月27日には、愛媛大学地域協働センター西条にて、写真選定のディスカッションを行いました。候補の写真は、自噴水だけでなく、農作や民謡、都市景観など幅広く、メンバーそれぞれの思い入れのポイントも多様で、写真の選定は難航しましたが、白熱した議論の後、メンバー納得の4枚を選ぶことができました。
参考文献
- 総合地球環境学研究所編『未来へつなぐ人と水-西条からの発信-』(2010年)
- 西条史談会『西條史談』
- 西条市・西条市観光物産協会『西条市水めぐりマップ歩き&車コース』
愛媛大学の研究まとめ
「えひめ瀬戸内LINKプロジェクト」の中で、東予地域の高校生とタッグを組み活動した愛媛大学 社会共創学部 井口研究室の皆さんに、各テーマの研究をまとめてもらいました。
クリックで拡大
さらに詳しく知りたい方はこちら
(外部サイトへリンク)
撮影場所Map
第4回 高校生による歴史文化PRグランプリ